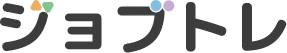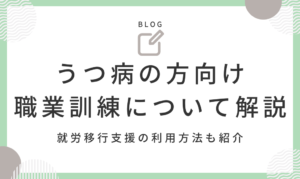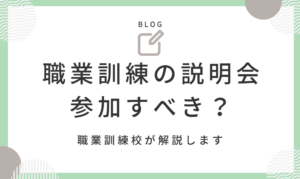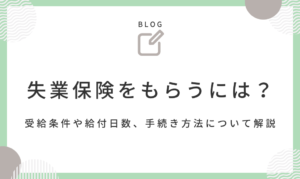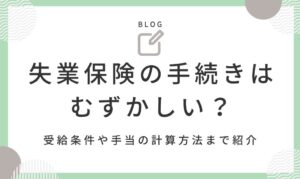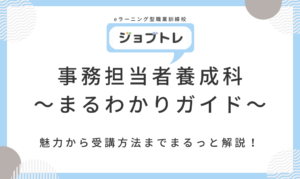うつ病でも職業訓練は受講できる|面接に受かるコツや就労移行支援との違いも解説

うつ病を患っている人の中には、職業訓練を受講して就職を目指したいと考える人もいるでしょう。
職業訓練は、就職する意思があればうつ病の人でも受講できます。
ただし、自身の体調など現状を考慮しておかないと、せっかく受講したのに退学することにもなりかねません。
そこで本記事では、うつ病でも受講できる職業訓練から訓練の面接に受かるコツまで解説しています。
記事を読むと、就労移行支援についても理解が深まるので、ぜひ参考にしてください。
ちなみに、最近では完全オンラインかつ受講費無料で受けられる職業訓練があるんです。
完全オンラインの職業訓練の雰囲気をサクッと知るには無料体験講座がおすすめですよ!
↓↓↓以下のバナーから公式LINEに登録して、体験動画を見てみてください↓↓↓

目次
うつ病でも職業訓練は受講できる
就職する意思があれば、うつ病の人も職業訓練を受講できます。
職業訓練は、訓練の種類によって通学期間や受講方法が異なります。
それぞれの理解を深めるために、以下の4つの項目を見ていきましょう。
- 職業訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」がある
- 求職者支援訓練は在宅で受講できるコースが豊富にある
- 公共職業訓練では国家資格や専門スキルが学べるコースがある
- 職業訓練を受講するまでの流れ
自分の状況に合わせた職業訓練が選べるように、詳しく解説していきます。
職業訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」がある
職業訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2種類があります。
それぞれの違いは、以下の表を参考にしてください。
| 職業訓練の種類 | 訓練期間 | 1日の授業時間 | 選考試験 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 公共職業訓練 | 3カ月〜2年 | 約3〜6時間 | 筆記試験と面接 | 失業保険の受給資格が必要 |
| 求職者支援訓練 | 3カ月〜6カ月(※) | 約6時間 | 原則、面接のみ | 失業保険の受給資格は必要ない |
失業保険の受給資格がある方は、公共職業訓練と求職者支援訓練のどちらも受講できます。
しかし、一方で失業保険の受給資格がない方は、求職者支援訓練のみしか受講できません。
それぞれの訓練で受講できるコースについて詳しく知りたい方は「職業訓練おすすめコース12選を一覧で紹介|公共職業訓練・求職者支援訓練」もあわせてご覧ください。
(※)一部のコースでは2カ月の場合もあります。詳しくは「求職者支援訓練に係るカリキュラムの作成に当たっての留意事項」を参照ください。
求職者支援訓練は在宅で受講できるコースが豊富にある
求職者支援訓練では、在宅で受講できるコースが豊富にあります。
そのため、他の受講者が気になったり、通学に不安があったりする方でも受講しやすい訓練です。
実際に、オンラインで求職者支援訓練を受講できる「ジョブトレ」の在籍者の中にも、体調に少し不安を感じつつも、工夫しながら訓練を受けている人がいます。
訓練に加えて「キャリアコンサルティング相談」や「就活個別相談」もオンラインで実施しているので、就職活動の悩みも解決しやすい環境です。
「ジョブトレ」について気になる方は、以下のリンクからLINEに登録して「無料講座」を試してみてください。
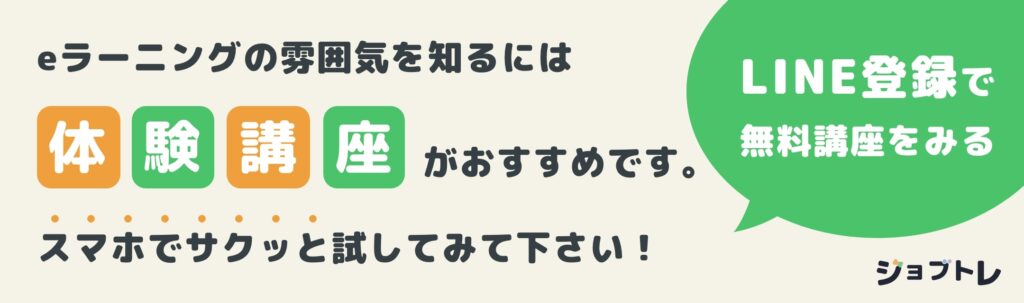
公共職業訓練では国家資格や専門スキルが学べるコースがある
公共職業訓練では、国家資格や専門スキル取得を目指したコースがあります。
専門人材育成訓練といって、訓練期間が1〜2年になる点が特徴です。
受講できる訓練の例は、以下のとおりになります。
- Web動画クリエイター
- アプリ・Web制作
- ゲームクリエイター
- 税理士
- 調理師
申し込むには、ハローワークの職業相談で訓練の必要性が認められなくてはなりません。
また、受講料以外の費用については自己負担になるため、事前に確認しておく必要があります。
募集期間中の訓練について詳しく知りたい方は「ハローワークインターネットサービス – 職業訓練検索・一覧」で検索してみましょう。
参考:訓練情報の検索のしかた
職業訓練を受講するまでの流れ
職業訓練を受講するまでの流れは、以下のとおりです。
- ハローワークで求職申込をする
- ハローワークで職業相談をする
- 受講申込書を作成・提出する
- 職業訓練の選考試験を受ける
- 職業訓練の合否を確認する
- 合格後、ハローワークで就職支援計画書の交付を受ける
申込書の書き方や注意点について詳しくは「職業訓練の申し込みの流れ8STEP|申込書の書き方や必要なものも解説」にまとめています。
手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
うつ病でも職業訓練の面接に受かる3つのコツ
うつ病でも職業訓練の面接に受かるコツは、以下の3つです。
- 体調面で懸念事項があるなら事前に伝える
- 出席については前向きな回答を心がける
- 事前に質問に対する回答を考えておく
面接に受かる確率を上げるために、順番に見ていきましょう。
1.体調面で懸念事項があるなら事前に伝える
面接では、体調面に懸念事項があるなら事前に伝えておくと良いでしょう。
たとえば「ジョブトレ」では「長時間パソコンに向かって受講できるか」「他の受講生とオンラインミーティングで交流できるか」といった点が受講に影響します。
そのため、懸念事項を面接で伝えることで、配慮を検討してもらえる可能性があります。
受講後の不安を減らすためにも、懸念事項は正直に相談しておきましょう。
2.出席については前向きな回答を心がける
職業訓練では、やむを得ない理由を除く欠席(遅刻・欠課・早退を含む)が認められません。
そのため、面接で出席について後ろ向きな回答をしてしまうと、選考に落ちる可能性が高まります。
どうしても体調面に不安があって欠席する可能性が高い場合は、障害者訓練を選択することも一つの手段です。
障害者訓練について気になる方は「障害者でも職業訓練は受講できる|障害年金をもらいながら受給できる手当・給付金も紹介」でまとめています。
注意点や給付金まで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
3.事前に質問に対する回答を考えておく
職業訓練の面接に受かるためには、質問に対する回答を事前に考えておきましょう。
よくある質問は、以下のとおりです。
- 志望動機
- 前職を退職した理由
- 就職活動の状況
- 訓練後に就きたい職業
また、職業訓練の説明会に参加すると、詳しい訓練内容や就職先についての情報が得られます。
志望動機や訓練後の就職先を考える上で参考になるので、説明会にはできる限り参加しておきましょう。
職業訓練の説明会に申し込む方法は「職業訓練の説明会は不参加でも合格できる?訓練校が解説」で詳しくまとめています。
うつ病の人は就労移行支援も利用できる
うつ病の人は、職業訓練の他にも「就労移行支援」で就職活動のサポートを利用できます。
就労移行支援について、以下の3つの項目を見ていきましょう。
- 就労移行支援では職場定着までサポートを利用できる
- 就労移行支援と職業訓練の違い
- 就労支援を利用する流れ
職業訓練との違いまで、詳しく解説していきます。
就労移行支援では職場定着までサポートを利用できる
うつ病の人は、就労移行支援で就職活動のサポートを利用できます。
就労移行支援とは、障害のある方の就労に向けたトレーニングや、就職後も職場に定着できるようにサポートを行う「障害福祉サービス」の一つです。
利用するための条件は、以下のとおりになります。
- 一般就労を目指していること
- 65歳未満であること
- 精神障害・知的障害・発達障害・身体障害などの障害がある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となる難病などのある方
また、障害者手帳の有無に関わらず、医師や自治体の判断で利用できます。
ただし、ハローワークの就職支援とは異なり、利用期間に制限がある点や利用料が有料である点には注意しておきましょう。
就労移行支援と職業訓練の違い
就労移行支援と職業訓練の違いは、以下の表をご覧ください。
| 職業訓練 | 就労移行支援 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 求職している人 | 求職している障害者 |
| 失業保険の受給 | ○ | ○ |
| 失業保険の受給延長 | ○ | X |
| 障害年金 | ○ | ○ |
| アルバイトやパート | ○ | X |
| 就労に向けた訓練 | ○ | ○ |
| 職場定着サポート | X | ○ |
| 就職活動支援 | ○ | ○ |
| 利用期間 | 2カ月〜2年 | 原則2年 |
| 利用料 | 教材費のみ | 有(世帯の収入による) |
大きな違いは、対象者を障害者に限定しているかどうかです。
そのため、就労移行支援の方が、受講者の状況に合わせた配慮を受けながら訓練を進められます。
ただし、就労移行支援を利用中は、アルバイトやパートが原則禁止されています。
職業訓練と就労移行支援を検討する際は、体調面だけでなく生活費についても考慮しておきましょう。
就労移行支援を利用する流れ
就労移行支援を利用する流れは、以下のとおりです。
- 利用する就労移行支援事業所を探す
- 就労移行支援事業所を見学する
- 居住地の障害福祉課で「障害福祉サービス受給者証」を申請する
- 就労移行支援事業所と利用契約を交わす
- 就労移行支援の利用を開始する
また、障害福祉サービス受給者証の申請には、以下の3点が必要になります。
- 印鑑
- 住所・氏名がわかるもの(運転免許証やマイナンバーカード)
- 障害者手帳または医師の診断書や通院記録
お近くの就労移行支援事業所を探すときは「障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET」を利用すると、市区町村まで細かく検索できます。
うつ病の人は職業訓練と就労移行支援のどちらを選ぶべき?
就職を目指しているうつ病の人の中には、職業訓練と就労移行支援のどちらを選ぶか迷う人もいるでしょう。
それぞれに向いている人の特徴を詳しく解説していくので、選ぶ際の参考にしてください。
職業訓練に向いている人の特徴
職業訓練に向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- 週5日の授業を受講する体力がある
- 失業保険の受給延長を希望している
- 訓練中にアルバイトやパートを検討している
- 就労移行支援に希望の訓練がない
- 短期間で就職を目指している
職業訓練では、多種多様なコースがあるためニーズに合わせた専門スキルを習得できます。
また、短期間で集中して訓練を行うので、早期就職も目指しやすい点がメリットです。
しかし、うつ病の各症状に応じた配慮が「就労移行支援」に比べて少ない場合もあり、学習ペースについていけないことも想定されます。
そのため、週5日の授業を受講する体力があるかどうかは、申し込む判断の基準の一つになるでしょう。
できる限り負担を抑えて職業訓練を利用するなら、オンラインで受講できるコースが最適です。
オンラインで受講できる職業訓練については「オンライン(eラーニング)の職業訓練|授業内容と面接対策を紹介」でまとめているので、参考にしてください。
就労移行支援に向いている人の特徴
就労移行支援に向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- 自分のペースに合わせた訓練スケジュールを希望している
- 障害に応じた配慮を求めている
- 訓練中に働かなくても生活に困らない
- 生活面やメンタル面の改善も目標にしている
- 職場定着までサポートを希望している
就労移行支援では、個々の状況に合わせた訓練カリキュラムで就職を目指せます。
たとえば、「まずは週1から訓練を始める」といったように通所のペースや、訓練内容なども自分に合わせて決められます。
しかし、中長期的に訓練を行なっていく特性であるため、すぐに働かなければいけない状況の人には向いていません。
また、原則として就労移行支援の利用中は、アルバイトやパートが禁止されています。
生活費に不安がある方は、失業保険や障害年金などを受給しながら、就労移行支援の利用を検討しましょう。
失業保険の手続きについては「失業保険をもらうには?|受給条件や給付日数、手続き方法について解説」にまとめているので、合わせてご覧ください。
うつ病でも職業訓練や就職移行支援で再就職できる
うつ病であるからといって、就職できないことはありません。
不安を抱えている場合でも、職業訓練や就労移行支援の利用で就職の可能性を高められます。
さらに就職の可能性を高めるために、以下の3つの項目も確認しておきましょう。
- うつ病に向いている仕事
- うつ病に向いていない仕事
- うつ病でも働きやすい仕事選びのコツ
職業訓練や就労移行支援のコース選択にも役立つので、順番に詳しく解説していきます。
うつ病の人に向いている仕事
病状や性格にもよりますが、うつ病の人は一般的に人との関わりが少ない仕事に取り組みやすさを感じる人が多い傾向です。
この記事でも、人との関わりが少ない職種の中から、うつ病の人に向いている仕事を紹介します。
具体的には、以下のような職種が向いていると言えるでしょう。
- システムエンジニア
- Webデザイナー
- Webライター
- 経理・事務
- 運送業
うつ病の人は、人間関係にストレスを感じやすい特徴があります。
そのため、システムエンジニアやWebデザイナーなどWeb関連のスキルをつけて、在宅ワークで働くことも一つの手段です。
また、マニュアルが整備されている事務職などは、想定外の状況への対応も少なく、心理的負担を減らせるでしょう。
未経験の業界への転職には、職業訓練を活用すると成功しやすくなります。
うつ病と向き合いながら転職を考えている人は「職業訓練は転職に不利?就職につなげる方法やメリットデメリットを解説」もあわせてご覧ください。
うつ病の人に向いていない仕事
うつ病の人は、一般的には対人関係が多い仕事や、ノルマが厳しい仕事に働きづらさを感じる人が多い傾向です。
この記事では、仕事内容に対人要素やノルマが含まれる職種の中から、うつ病の人に向いていない仕事を紹介します。
具体的には、以下のような職種が向いていないと言えるでしょう。
- 営業
- 接客業
- 管理職
- コールセンター
仕事にストレスを感じる原因には「仕事の量」「仕事の質」「対人関係」などが挙げられます。
ストレスを避けるためには、ノルマが厳しい仕事や対人要素が多い仕事は避けるべきです。
また、職種以外にも職場の雰囲気が合わない可能性も考えられます。
職場見学に行ったり、口コミを調べたりすることで、就職後のミスマッチを避ける努力も必要です。
就職後のサポートも受けたいと考えている方は「うつ病の人は就労移行支援も利用できる」を参考にしてみてください。
うつ病の人でも働きやすい仕事選びのコツ
うつ病の人でも働きやすい仕事を選ぶコツは、以下のとおりです。
- 自分の症状を理解する
- 就職活動の期間を長期で考える
- 障害者雇用への応募も視野に入れる
うつ病の症状は、精神面と身体面においてさまざまあります。自分にどんな症状が出るか把握することで、向いている仕事の選択肢を絞ることが可能です。
ただし、就職活動の期間を短く見積もると、焦りや不安から症状を悪化させるかもしれません。
余裕を持ったスケジュールを組んで、体調に配慮しながら就職活動をおこないましょう。
また、うつ病の人でも「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けていると障害者雇用へ応募できます。
障害者雇用で働くと、働くうえで配慮を受けやすくなります。
障害者雇用について詳しく知りたい方は「ハローワークインターネットサービス – 障害のある皆様へ」をあわせてご覧ください。
FAQよくある質問
職業訓練を受講中に傷病手当は受給できる?
職業訓練の受講中は、傷病手当は受給できません。
なぜなら、職業訓練は就職できる状態の人を対象にしているからです。
傷病手当を受給している人が職業訓練を受けるためには、回復したという医師の証明書が必要になります。
また、失業保険についても傷病手当とは併給できません。
退職後も傷病手当を受給する場合は、忘れずに失業保険の延長手続きをおこないましょう。
失業保険の延長手続きについては「失業保険の延長条件|もらい方と職業訓練のメリットも紹介」で詳しく解説しています。
ハローワークにうつ病でも応募できる求人はある?
うつ病の人でも、ハローワークの「職業相談」や「求人検索」を利用して求人に応募可能です。
職業相談では「うつ病がある状態での就職活動」や「面接や履歴書の対策」についての疑問も解決できます。
また、さまざまな支援も利用できるので、詳しく知りたい方は厚生労働省の「障害者の方への施策 |厚生労働省」も参考にしてください。
うつ病で退職すると失業保険は受給できる?
うつ病で退職したとしても、条件を満たすと失業保険は受給できます。
具体的な条件については、以下のとおりです。
- うつ病を発症していても働ける状態であること
- ハローワークに求職申込していること
- 失業の状態であること
- 就職する意思や能力があること
- 離職の日以前2年間に雇用保険の加入期間が12カ月以上あること(自己都合退職の場合)
- 離職の日以前2年間に雇用保険の加入期間が6カ月以上あること(会社都合退職の場合)
うつ病の症状が重くて働ける状態にない人や、治療に専念するために就職活動を行わない人の場合は、失業保険の受給はできません。
失業保険の手続きについては「失業保険の手続きをわかりやすく解説|受給条件や手当の計算方法まで紹介」にまとめています。
うつ病で職業訓練を受講した後に就労した事例はある?
オンラインで求職者支援訓練が受講できる「ジョブトレ」では、精神疾患がある方で事務系の仕事に就職された実績があります。
「ジョブトレ」の訓練コースは自宅で受講できるので、メインの動画学習中は体調に合わせて自分のペースで受講できます。
また、地域外の訓練コースでも全国から応募できるため、比較的受講しやすい職業訓練といえます。
「ジョブトレ」で受講できるコースについて興味がある方は「ジョブトレ事務担当者養成科まる分かりガイド〜魅力から受け方までまるっと解説!〜」を参考にしてください。
さいごに
本記事では、うつ病の人が受講できる職業訓練について解説してきました。
就職する意思があれば、うつ病の人も職業訓練の受講が可能です。
ただし、職業訓練校では、体調面や精神面のサポートが受けられない可能性があります。
スキルが身につくまで職業訓練を継続できるように、自身の状況にあわせた訓練選びが重要です。
例えば、人付き合いや外出が苦手な方は、自宅からオンラインで受講できる職業訓練を選ぶと良いでしょう。
ちなみに「ジョブトレ」も、オンラインで講座が受講できる求職者支援訓練校です。
訓練の他にも「就活個別相談」や「キャリアコンサルティング」も利用できるので、充実した転職サポートを求める人に向いています。
気になる方は、以下のリンクからLINEに登録して「受講診断」を試してみてください!
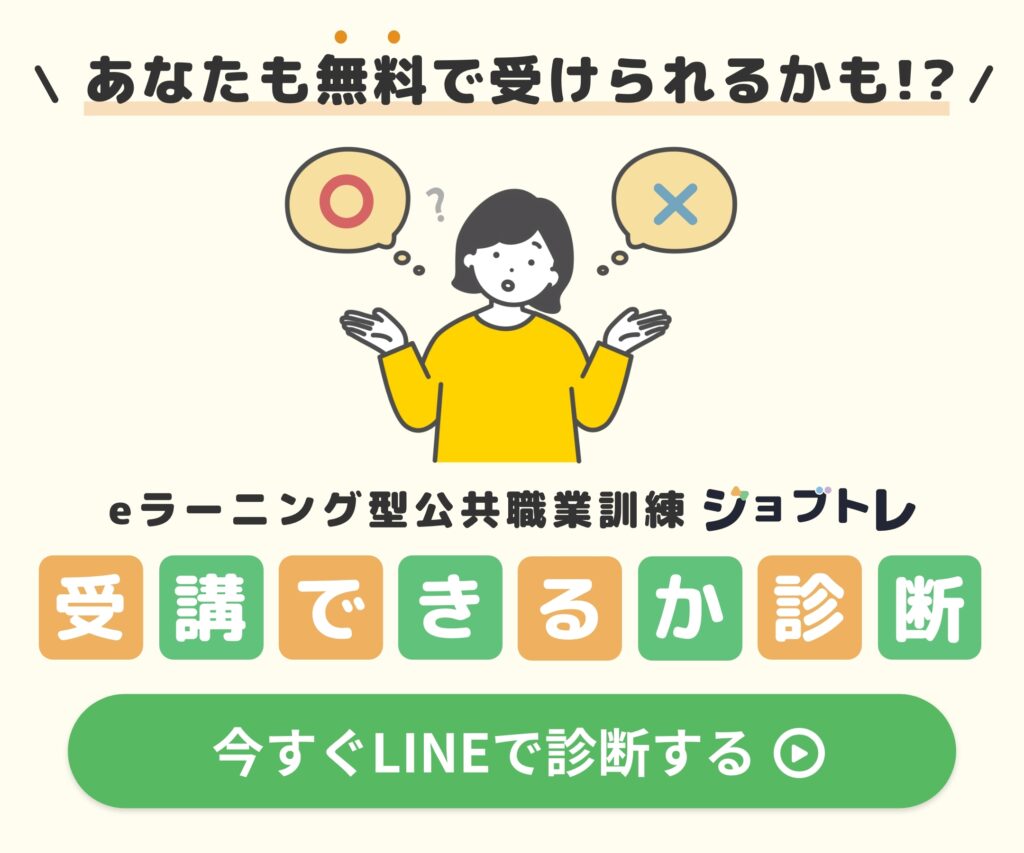
監修者

平原正浩
ワークキャリア株式会社 求職者支援訓練 本部運営チームリーダー
ワークキャリア株式会社の本部にて、職業訓練校「ジョブトレ」の運営業務全般を統括する。主な業務は訓練制度の把握や訓練運営体制の整備、開校申請など。
ライター

いしい ゆうすけ
Webライター
ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にて、SEOメディアの執筆を担当。過去に販売職から営業職への転職経験あり。自分自身が悩みながら行動した経験をもとに、読者の問題解決につながる記事を目指して執筆している。